謎めいたエックス博士
第二章 世から消える

「聞いた?聞いた?」アンドリア・マロンは教室の自分の席に座るピーターに叫びかけた。
「何を?」ピーターは少し気が散った様子で聞き返した。彼はまだ夢のことでとらわれていたのである。
「サリバン先生は溺れたのよ。彼女は窒息して死亡したの!」と彼女は叫んだ。
クラスの大勢の人たちがびっくりして振り向いた。そしていっせいにしゃべりだした。
「えっ!」
「本当に?」
「どうして知っているの?」
その間、ピーターの足は震えていた。そんな…
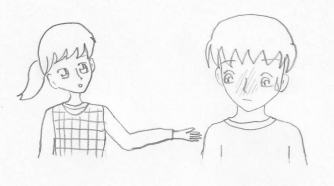
「大丈夫?」ソフィア・リンドバーグは心配そうに聞いてきた。ソフィアはピーターの仲のいい友達だった。彼女はいつも優しく、普段だったらピーターは彼女が話しかけてくれるととても嬉しかった。しかし、今日はほとんど彼女がそこにいることすら気づかなかった。アンドリアの言葉が頭の中でぐるぐる回っていた。『サリバン先生は溺れたのよ。彼女は窒息して死亡したの…死亡した…死亡した…』突然全てが真っ暗になった。

ピーターは目が覚めて、たくさんの黒い穴のあいた天井を見た。保健室の天井だった。
「彼は意識を取り戻したみたいよ!」と看護婦は大声で言った。そして彼に優しく微笑みかけ、「やっと起きたのね、寝坊助さん。何時間も待っていたのよ。」と言った。
看護婦はピーターの家に電話したが、誰もいなかった。ピーターは彼女に自分の父がどこで働いているのか教えた。彼女はそこへ電話し、ピーターのお父さんは仕事から早く帰り、ピーターを迎えに行った。

「で、調子はどうなんだね?」とピーターのお父さんはバックミラーでピーターのことを見ながら聞いた。
「大丈夫だよ。」とピーターは嘘をついた。まだ頭がくらくらした。まるで、ぐるぐる回って止まらないジェットコースターに乗っているようだった。しかし、彼は父を仕事から早く帰らせてしまったことだけで十分罪悪感を感じていた。父に心配をかける必要はないと考えた。
ピーターはすぐにベッドに入った。疲れてはいたが、全く眠れなかった。なぜだかわからない。『どうして僕はそもそも気絶したのだろう?』彼はかすかにショックを受けたということは覚えていた。しかし、何でショックを受けたかは覚えていない。厚い霧が彼の脳を取り巻いているようだ。
彼はイラついてため息をついた。そして、ベッドから起き上がった。寝られないなら、勉強でもするか。机の中から理科の問題集を取り出した。机の上には、彼が小さい子供だった頃に亡くなった、母の写真があった。彼女は青のマフラーとカーディガンで美しく見えた。

その時、彼は凍りついた。昨日の夢がよみがえると同時に彼はゆっくりと思いだし始めた。彼の母は難病にかかってベッドで横たわっていたのを思い出した。皆パニックし、怖がり、無力だった。ある人がこの世から消える寸前だった…誰もその人の死を止める力を持っていなかった…
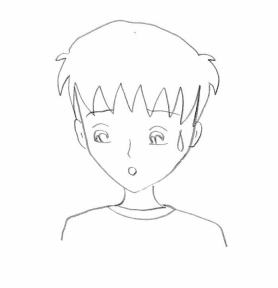
彼はサリバン先生が亡くなったと聞いて気絶したのであった。彼は母の写真をじっと見ながら、涙がこみ上げてきた。とても信じられない。ついこの前話したばかりなのに。彼女は彼がノーベル賞を受賞したらそこにいてくれると約束したのに。もうそれは起こりえない。なぜなら彼女は死んでしまったからである。ピーターはその恐ろしい言葉に身震いした。彼はもう彼女の話や笑い声を聞けないし、優しい笑顔も見られない…
本当に誰かに慰めてもらいたかった。父にこのことを言いたかったが言えなかった。最近、父から少し距離を感じていた。それは、ピーターの父が仕事ばかりに専念していたためである。ピーターの父は日曜日しか家にいなかった。ピーターはほとんど父と一緒にいることがない。寂しさが彼の心をぎゅっと握った。彼は、世界から消えたいと願った…母やサリバン先生のように。

ピーターは温かい光が自分を囲むのを感じた。『僕は天国にいるのかな?』と彼は考えた。彼は目を開き、ただの窓から射している日の光であることに気づいた。机で寝てしまった。彼は手の中に母の写真をしっかり握っていたことに気づいた。彼は悲しそうに机に写真を戻した。
まだ朝の五時半だったが、彼は起き上がって下に行った。キッチンのドアを開けた。父が中にいたのに驚いた。
「何でそんな早起きしてるの?」とピーターは聞いた。
「あれ、言わなかったっけ?今日は少し早く仕事に行くんだ。冷蔵庫には昨日の夕飯の残りがあるから。電子レンジで温められるよ。」
ピーターは不機嫌そうにうなずいた。

「それで君は?何でそんなに早くに起きたんだい?元気になったか?」
「あぁ、僕は元気だよ。」とピーターは小声で言った。ピーターは父が本当は心配してないのに心配してそうに見せるときが大嫌いだった。
しばらくの間、緊張の漂う沈黙があった。ピーターは、父が音を立てながら新聞を読み時々咳する中、静かに食べていた。
ピーターは、気まずさをカバーするためにラジオをつけることにした。
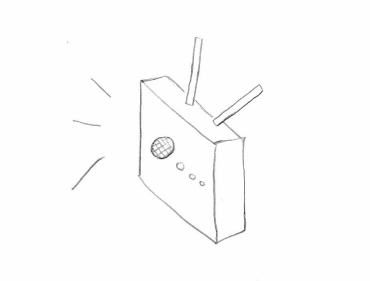
「…地元の中学教師のクリスティナ・サリバンさんは、ココナット・ビーチの岸辺から遠く離れた船の事故により亡くなりました。」
ピーターの目は大きくなり、彼はラジオの音量を上げた。
「ボートは小さな爆発を起こし、沈没しました。ボートが爆発すると同時に、木のかけらがはがれて飛び散りました。警察はこの爆発は故意的と考え、殺人なのか自殺なのかを知ろうとしています。サリバン先生のご遺体は発見されていないのですが、彼女は岸にたどりつかなかったので、死亡したものと思われます。」
「ふむ、こんなことがこの町で起きるなんて信じられないな。俺はこの町の犯罪の少なさをいつも誇りに思っていたのに。」ピーターの父はそう言いながら、また一ページ新聞をめくった。

ピーターは父が自分の大好きな理科の先生が亡くなったということを知らないことに気づいた。『まぁ、知らないなら言う必要もないか。』とピーターは考えた。最近、彼は父から注目を受けるのを恥ずかしく気まずく感じるようになってきた。それぐらい二人の間には距離があったのである。

数分後、ピーターは家を出て、弟のスコットと一緒に学校へ行った。スコットはピーターより二歳年下だった。しかし、二人の間のギャップは五年ぐらいに見えた。ピーターは、責任感があって思慮深かった。しかし、スコットはいたずら好きで衝動的だった。ピーターの父はほとんどの時間いないので、ピーターがスコットの面倒を見なければいけなかった。スコットの面倒を見るのは大変な仕事だった。それでも、二人は普通の兄弟のごとく仲が良かった。

学校へ着いたら、ピーターは「バイバイ。」とスコットに手を振った。そして深呼吸をし、教室に入った。彼は今日理科の授業があった。誰が新しい先生になるのか気になった。
戻る
Copyright ©2020 Author Lemon All Rights Reserved.